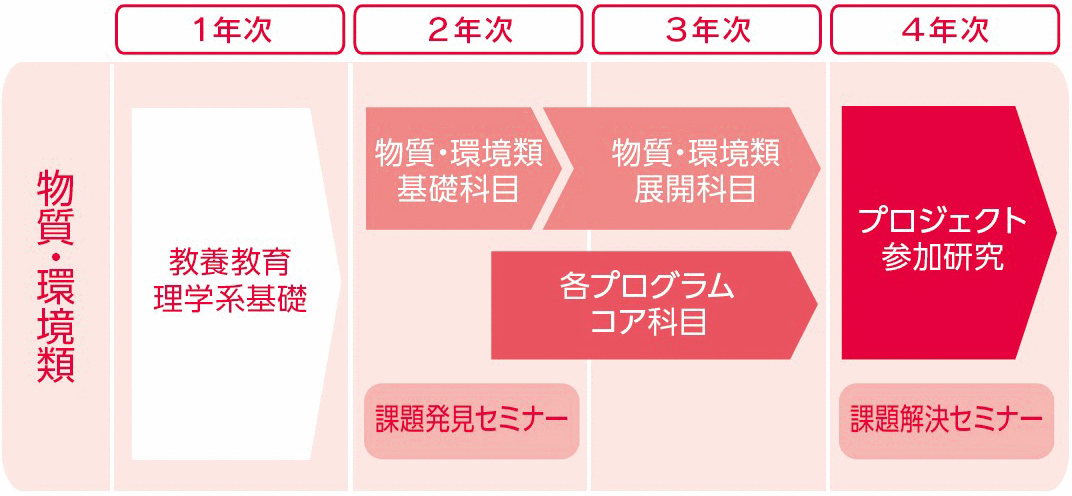カリキュラム
カリキュラムツリー
全ての科目は有機的につながり、卒業までの学びの道標(みちしるべ)を形作ります。
4年間の学びの流れ
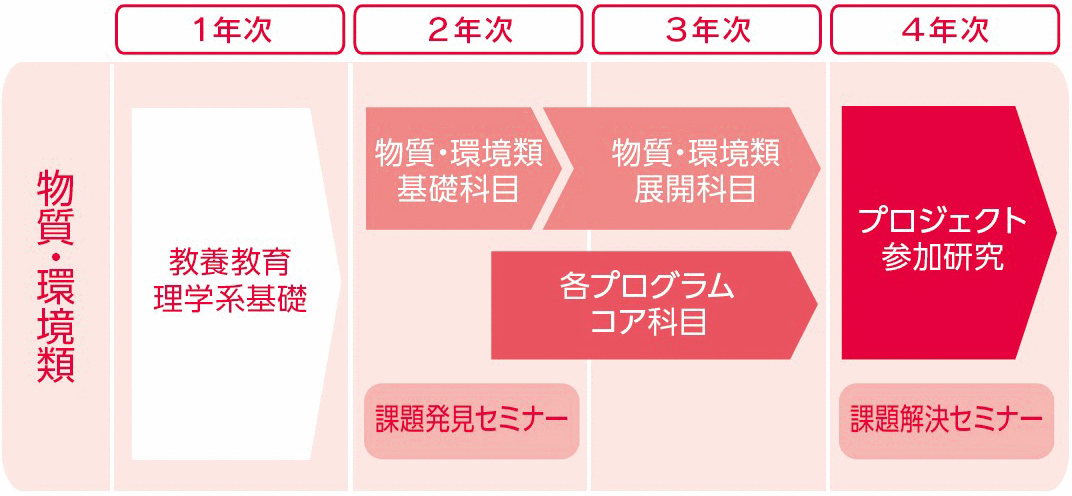
モデルカリキュラム
| 1年次 |
数学入門 物理学入門 物質・環境概論 基礎化学実験 生物化学 物理化学 学びのリテラシー データサイエンス ほか
科目ピックアップ
【学びのリテラシー】
少人数のゼミ、講義、演習を行います。各教員が専門としている分野を中心に、課題の見つけ方、分析の仕方、発表の方法、文章のまとめ方など、これからの大学での学びにおいて求められる基本的な方法を修得します。さらに、各学問分野に共通の思考力・判断力・表現力等を養い向上させることを目指します。
|
| 2年次 |
プログラミング基礎 物質・環境基礎実験 課題発見セミナー 安全工学・技術者倫理 インターンシップ ほか
科目ピックアップ
【課題発見セミナー】
企業で働くことの最低限のマナー、企業の現状などについて、座学やグループ学習により課題を把握します。さらに、実際の職場の見学や就労体験を行い、すべての学生が実社会の活動における課題について自主的に把握できるようにします。学生は各自把握した課題について、成果をまとめ発表会などを通して報告します。
■応用化学プログラム
分子生物学 無機化学 有機反応化学 応用化学実験 ほか
■食品工学プログラム
群馬県の食品工業概論 食品分析 微生物学 食品科学実験 ほか
科目ピックアップ
【群馬県の食品工業概論】
日本および世界の食品産業と食品工学の関係について学んだ上で、日本における群馬県食品産業の位置づけと特徴について解説します。また食品工学プログラムのカリキュラム構成と今後学ぶべき分野・項目を理解し、履修計画を自発的に立てられるよう、指導します。さらに食品工学の更なる発展のために必要とされる観点や人材像について考察します。
■材料科学プログラム・化学システム工学プログラム
化学工学基礎 金属材料学 高分子化学 エネルギー材料科学実験 ほか
■土木環境プログラム
地域の環境と安全 構造力学 コンクリート工学 土と地盤の力学 ほか
科目ピックアップ
【地域の環境と安全】
学生を少人数グループに分け、各グループには教員一人がついて指導を行います。「地域の安全と環境」という総合題目に関わる独自のテーマを学生が主体となって定め、設定した課題の検討及び成果のとりまとめを行うとともに、最終的に発表を行います。
|
| 3年次 |
偏微分方程式 専門英語 知的財産専門講座 経営工学 ほか
■応用化学プログラム
細胞生物学 構造化学 生物有機化学 応用化学演習 ほか
科目ピックアップ
【応用化学演習】
これまでの講義で学習した内容の理解度を深めるために、演習形式で復習・実習を行います。講義で学んだ様々な重要概念を、演習内でも再度解説することにより講義内容を復習し、その上で演習問題を解くことにより実践力を習得することを目指します。
■食品工学プログラム
食品衛生学 食品生産工学実験 食品機能工学 包装工学 ほか
■材料科学プログラム
材料加工学 無機材料学 材料強度学 材料科学実験 ほか
科目ピックアップ
【材料科学実験】
実験操作の手法を修得するとともに、金属材料、有機材料、無機材料、高分子材料などの構造・性質に関しての理解を深めることを目的とします。様々な実験を行い、材料に関して理解を深め、実験レポートを作成することで、論理的思考法、表現法を修得します。
■化学システム工学プログラム
反応工学 プロセスシステム工学 化学システム工学演習 ほか
科目ピックアップ
【化学システム工学演習】
化学工学の総合的な理解を目的として、物質収支、移動現象論、反応工学、プロセスシステム工学、化学熱力学、電気化学、工業化学などの学習に必要な基礎的な知識の再確認と理解を深めるための演習を行います。
■土木環境プログラム
河川防災学 交通・都市開発工学 防災計画 建設設計製図 ほか
|
| 4年次 |
課題解決セミナー プロジェクト参加研究 ほか
科目ピックアップ
【課題解決セミナー】
2年次の課題発見セミナーでの体験を基に、学生が自らテーマを設定して、課題解決にあたるグループを作ります。グループはプログラムを横断したメンバー構成とし、異なる専門の学生や企業人と交流することで、実践を通して新たなモノの創造の足掛かりを学びます。
|